
コミュニケーション能力を高めたいけれど、何から始めれば良いかわからない人は多くいます。コミュニケーション能力に悩みを持つ人にとって、文章読解・作成能力検定は注目の解決策です。この記事では、文章読解・作成能力検定の概要や出題範囲、効果的な勉強方法をわかりやすく解説します。
記事を読めば、文章読解・作成能力検定にチャレンジする方法がわかります。文章読解・作成能力検定に合格できれば、読む力や書く力、コミュニケーション能力全般の向上が可能です。
» ライターになるには?基礎知識と未経験から始める方法を解説!
文章読解・作成能力検定とはコミュニケーション力を高める検定

文章読解・作成能力検定は、日常生活やビジネスシーンで必要とされる読み書きの能力の測定を目的としています。文章読解・作成能力検定では、読解力や要約能力、文章を構築する力など、言語に関する総合的なスキルが評価されます。初級から上級までがあり、自分の能力に合わせて段階的にスキルアップが可能です。
文書作成スキルも問われ、実務で即戦力となる能力が身に付きます。学生から社会人まで幅広い層が対象です。文章読解・作成能力検定は、能力証明や就職・昇進に役立つ資格としても活用されており、コミュニケーション力の向上も可能です。
文章読解・作成能力検定の概要

文章読解・作成能力検定の情報を詳しく解説します。
出題形式
文章読解・作成能力検定は、各級に応じた出題形式が設定され、問題形式はさまざまです。四択問題や記述式問題があり、読解セクションと作成セクションに分かれています。読解セクションでは、時事問題に関する文章理解が求められ、現代の出来事についての理解が必要です。
作成セクションでは、ロジカルシンキングを必要とする問題が含まれます。論理的で明確な文章作成能力が大切です。さまざまなスキルが試されるため、全体的な言語能力の向上を目指せる構成となっています。
試験時間
試験時間は級によって異なります。試験時間は以下のとおりです。
| 試験の級 | 試験時間 |
| 4級 | 60分 |
| 3級 | 75分 |
| 準2級 | 90分 |
| 2級 | 120分 |
試験時間は、各級の難易度に応じて設定されています。受験者は限られた時間内で問題を解き、自分の能力を試します。適切な時間管理が、試験で良い成績をとるための鍵です。
問題数

文章読解・作成能力検定における各級の問題数は、以下のとおりです。
| 試験の級 | 問題数 |
| 4級 | 40問 |
| 3級 | 45問 |
| 準2級 | 50問 |
| 2級 | 55問 |
問題数は、各級の難易度を反映して設定されています。試験の準備段階では、問題数を意識して効率的な学習計画を立てましょう。
合格基準
合格を目指すには、全問題の70%以上の正答が必要です。合格基準は各級に応じて設定され、読解力と文章構成能力の両方が総合的に評価されます。合格基準は年度によって微調整されるため、試験前に最新情報を確認しましょう。試験結果は、受験後約1か月で通知されます。
合格基準について理解して正しく準備すれば、試験の合格が近づきます。
申し込み方法

文章読解・作成能力検定は、公式ウェブサイトや指定された登録サイトを通じて申し込みが可能です。オンラインで必要な情報を入力し、登録を完了させます。申し込み時に、受験料の支払いが必要です。クレジットカードなど、指定の方法で支払いを済ませてください。
受験者は、受験日や受験会場、受験級を自分で選択します。申し込みが完了すると、受験票がメールまたは郵送で届きます。試験当日は、受験票を忘れずに持参してください。
受験料
受験料は級によって異なります。各級の受験料は以下のとおりです。
| 試験の級 | 受験料 |
| 4級 | 2,000円 |
| 3級 | 2,500円 |
| 準2級 | 3,000円 |
| 2級 | 3,500円 |
支払い方法は、オンラインや銀行振込に対応しています。支払い後の返金は原則として行われません。金額や級をしっかりと確認したうえで、申し込み手続きを進めてください。
受験会場
受験会場は、全国の主要都市に設置されています。公共交通機関へのアクセスも良好です。バリアフリー対応や十分な設備が整っており、快適に試験を受けられます。試験日の数週間前には、受験票と共に会場の詳細が案内されます。申し込み時に会場を選択し、受験者は事前に申し込んだ会場で受験しなくてはいけません。
受験者が試験に集中できる環境が準備されているため、安心して受験が可能です。
文章読解・作成能力検定の種類

文章読解・作成能力検定は、初級者から高度なスキルを持つ上級者まで、幅広いレベルに対応しています。日常生活やビジネスシーンで求められるコミュニケーション能力の向上を目的に設計されています。文章読解・作成能力検定の種類は、4級、3級、準2級、2級です。
文章読解・作成能力検定に1級はありません。現在実施されている最高レベルは2級です。各級ごとにスキルレベルが明確に定められ、受験者は自分の能力に応じた試験を選択できます。自分のスキルを客観的に評価し、スキルアップに活用してください。
4級
文章読解・作成能力検定の4級は、基礎的な日本語の読み書き能力を測る試験です。小学校高学年から中学生の学習水準に合わせて設計されています。4級で評価されるのは、文章の基本構造を理解する能力です。日常生活で頻繁に遭遇する簡単なテキストの読解力が問われます。短い文章を自ら作成する能力も、評価の対象です。
4級の学習を通じて、受験者は日常的なコミュニケーションで必要とされる基本的な言語能力を身に付けられます。
3級
文章読解・作成能力検定の3級では、中級レベルの文章能力が測定されます。3級で求められるのは、一般的なビジネス文書や複雑な文章を適切に理解し、表現する能力です。試験内容には、論理的な文章構成や要約スキルが評価される問題が含まれます。情報を整理し、説得力のある文章を作成する能力も重要なポイントです。
具体的なビジネスシーンでの応用が求められるため、実務に役立つスキルを身に付けるための絶好の機会です。文章読解・作成能力検定3級の学習を通じて、ビジネスでも通用するスキルを習得しましょう。
準2級

文章読解・作成能力検定の準2級では、読解力と文章作成能力を中級レベルで評価します。準2級のレベルは、社会人や学生がビジネスシーンで求められる、基本的な文書作成スキルを確かめるために設計されています。出題形式は記述問題が中心です。レポートや企画書など、一定の構成を持つ文書の読解と作成が問われます。
準2級に合格するためには、具体性と論理性を備えた文章を作成する能力が必要です。
2級
文章読解・作成能力検定の2級では、ビジネス文書や報告書など実用的な文書を正確に理解しなくてはいけません。要約や意見を述べる能力が問われます。2級の合格を目指すには、読んだ内容を整理し、論理的に分析する力が不可欠です。
多角的な視点からの情報整理能力も求められるため、日常的にさまざまな種類の文書に触れましょう。多様な文書をどのように読み解くかを学ぶことが大切です。社会人として必要とされる高度なコミュニケーションスキルの向上のために、2級の文章読解・作成能力検定の受験は有効な手段です。
文章読解・作成能力検定の出題範囲
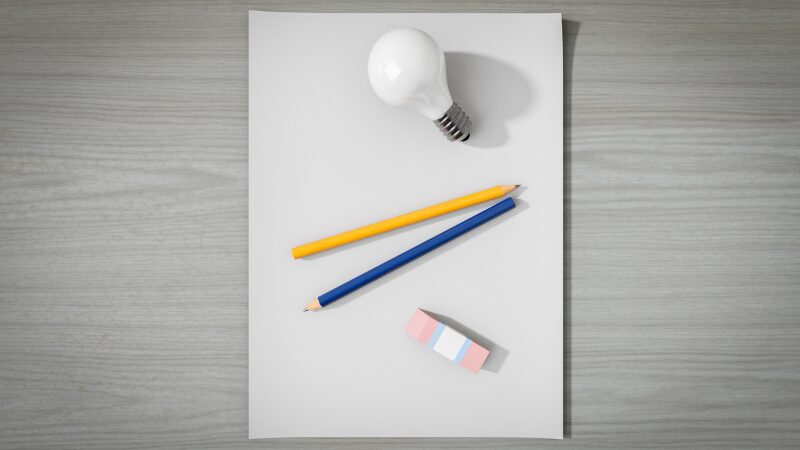
文章読解・作成能力検定では、以下の力が試されます。
- 基礎力
- 読解力
- 作成力
3つの能力は、日常生活やビジネスシーンにおいて重要です。文章読解・作成能力検定を通じて、それぞれのスキル向上が可能です。
基礎力
文章の基礎力を向上させるために、まずは正しい文法の理解が重要だと認識してください。文章の基本構造は、以下のとおりです。
- 主題
- 本文
- 結論
文法を正しく理解し適切に使えば、読み手にとって明瞭で理解しやすい文章を作れます。正しい句読点の使用も、文章の明瞭さを保つうえで大切な要素です。句読点によって、読み手はスムーズに文章を読み進められます。基本的な語彙力の向上も、文章力向上のためには不可欠です。
適切な言葉を選び、正確に使うことで、表現の正確性が向上します。語彙力は、日常のコミュニケーションだけでなく、ビジネスシーンでの効果的なコミュニケーションにも大きく貢献します。情報を的確に理解し、要約するスキルも、文章の基礎力を支える重要な要素です。
情報を正確に捉え、必要な情報を簡潔にまとめられると、より効率的で目的に合った文章を作成できます。基礎力にまつわるスキルを身に付ければ、簡潔で明瞭な表現が可能です。読者にとって理解しやすい質の高い文章を作成できるようになりましょう。文章力の向上のためには、基礎力が重要です。
読解力
読解力は、文章の主旨や要点を正確に把握するスキルです。比喩や象徴の解釈、文章構造の分析を通じて、より深い理解ができます。文章の導入から展開、結論に至るまでの流れを理解できる点も、読解力の重要な側面です。
作成力
効果的に文章を作成する力は、コミュニケーション能力の向上に直結します。文章を作成する際は、主張や理由を明確にし、読者が理解しやすい構造を心がけましょう。メールで依頼事項を伝える際には、具体的な要望を最初に書きます。理由や背景を続けて説明すると、受け手に明確で効果的に情報を伝えられます。
読者がどのように情報を受け取るかを意識すると、より有効です。文章の一貫性を保ち、読者に伝えたいポイントを適切に配置するスキルが重要です。
文章読解・作成能力検定の勉強方法

文章読解・作成能力検定は、読解力と文章作成能力を測るため、幅広いスキルが求められます。文章読解・作成能力検定の効果的な学習法について、以下の2点を解説します。
- 公式テキスト
- 過去問題集
計画的に学習し、記事作成の練習を重ねて実践力を高めましょう。
公式テキスト
文章読解・作成能力検定の準備において、公式テキストが役立ちます。公式テキストには、文章読解・作成能力検定の出題範囲すべてが含まれます。基本的な文法から高度な文章構成まで、幅広い知識を身に付けるのに最適です。実際の試験でよく出るポイントや解答のコツも含まれています。
公式テキストをうまく活用すれば、より実践的な対策が可能です。
過去問題集
過去問題集では、試験の形式や出題傾向を理解できます。各級に応じて市販されており、受験者が実際の試験の問題を事前に把握するのに役立ちます。過去問題集は、問題と正解の記載だけではありません。詳しい解説が付属しているため、試験問題の理解が深められ、似たような問題に出会った際の思考力も高められます。
過去問題集を定期的に解けば、試験時間内に効率よく問題を解く時間管理能力が身に付きます。試験の最新の傾向や変更にも対応するためには、最新の過去問題集を使用することが重要です。過去問題集を利用して、文章読解・作成能力検定の準備をしましょう。
文章読解・作成能力検定に役立つスキルの活用例

文章読解・作成能力検定で身に付けたスキルは、さまざまな場面で活用できます。日常生活やビジネスシーンにおいて、具体的にどのように役立つかを解説します。
ビジネスシーンでの応用
ビジネスにおいて、文章読解・作成能力は重要です。メールや報告書、プレゼン資料など、日々の業務で文章を扱う機会は多くあります。検定で学んだ論理的な構成力を活かせば、報告書や提案書の内容を簡潔で説得力のある内容でまとめられます。
読解力が高いと、取引先からの長文メールや契約書の内容を正確に理解することが可能です。業務のスピードと効率の向上につながります。
日常生活での活用
日常生活でも、文章を読む力や書く力が役立つ場面はあります。活用例は以下のとおりです。
- 子どもの学校からのお知らせを読み取る
- 要点を家族に共有する
- 自治体の案内文を理解する
- 必要な手続きをスムーズに行う
- SNSやブログで情報発信する
日常生活をより良くするために文章読解・作成能力は欠かせません。
» Webライターになるには資格は必要?おすすめの資格と選び方
まとめ

文章読解・作成能力検定は、コミュニケーション能力の向上を目指すための検定です。文章読解・作成能力検定を受けると、基礎力や読解力、作成力を総合的に評価され、各スキルの向上が期待できます。2〜4級のレベルが4段階で設定されており、自分の能力に合わせて挑戦できることも大きな魅力です。
公式テキストや過去問題集の使用が勉強方法として推奨されています。コミュニケーションスキルは社会人として必須の能力であるため、文章読解・作成能力検定は多くの人にとって有益です。